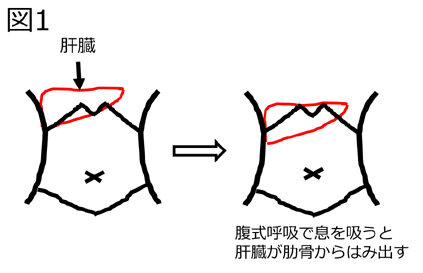
アルコール性肝障害
セントヒル病院 消化器内科
内田耕一
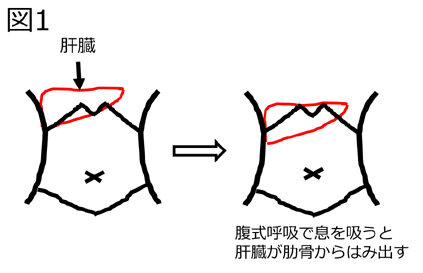
【アルコールの量について】
飲料に含まれるアルコールの量(グラム)は、量×濃度×比重で表すことができます。
ビール中ビン(缶ビールロング缶)(500ml)1本 20グラム
日本酒1合=21.5グラム
缶酎ハイ1本=20グラム
ワイン(12%)(120ml)=24グラム
ウイスキー、ブランデー、ジン、ウォッカ、ラム(40%) ダブル水割り1杯=20グラム
梅酒(13%) 1合(180ml)=19グラム
おおよそ厚生労働省が推奨している2ドリンクと言われるアルコール20グラムの量です。1回にこれ以上飲酒されている方は要注意と言えます。
【アルコール性肝障害診断基準】
2011年に出された診断基準によると「アルコール性」とは、長期(通常は5年以上)にわたる過剰の飲酒が原因と考えられる病態と定義しています。過剰の飲酒とは、1日平均純エタノール60g以上の飲酒(常習飲酒家)をいいます。ただし女性や下戸の方では、1日40g程度の飲酒でもアルコール性肝障害を起こすといわれています。
日本ではアルコール摂取量60g以上の多量飲酒者は、約860万人と言われています。女性は男性に比べ、より少ない飲酒量でも、短期間の飲酒でも重度の肝障害になりやすいことが報告されています。最近20〜40歳代の女性の飲酒率、多量飲酒者が増加しており注意が必要です。休肝日を最低でも1日おきに必ず作ることが大切です。
【アルコールによる肝臓の変化】(図2)
アルコールを多飲していると肝臓がアルコールを処理するために徐々に大きくなってきます。こうなると肋骨下縁から常時張り出した状態になります。アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎の状態が多いです。
[脂肪肝]可逆的であり、断酒により急速に改善します。しかし断酒しても10%は悪化するという報告があります。
[アルコール性線維症]肝組織中に線維の増生が認められる状態を言います。
[アルコール性肝炎]断酒することで約30%の人が、正常の状態に戻るといわれていますが、大半は肝炎が持続し悪化します。肝炎になる前に治療する(=断酒する)ことが大切です。
[アルコール性肝硬変]お酒を飲み続けると最終的に肝臓は硬く小さくなります。
肝硬変になると、黄疸や浮腫や腹水が溜まったり、食道や胃に静脈瘤といって血管の瘤ができ、吐血や下血をきたす場合があります。肝硬変からは肝臓癌が発生する場合があります。
自分の肝臓がどのような状態かは、自覚症状はほとんどありません。血液検査や画像検査を行い詳しく調べることが大切です。
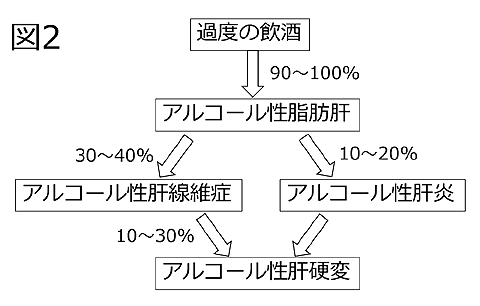
【アルコール性肝障害の合併症】
アルコールばかりを摂取していると、栄養素が不足してきます。よく知られているのがビタミンB1欠乏による意識障害や精神症状をきたす「ウェルニケ脳症」という脳の障害です。また末梢神経障害である「脚気」を起こす場合もあります。バランスよく栄養を摂取することが大切です。
【心にとめておいて頂きたいこと】
1. お酒を長く楽しむためには、1回量をセーブして、休肝日を必ず週半分はつくる!
2. 健康診断で肝機能異常を指摘されたら、外来を受診してご相談ください!
3. アルコール依存症の場合は、専門病院での加療継続、断酒会等への参加を!